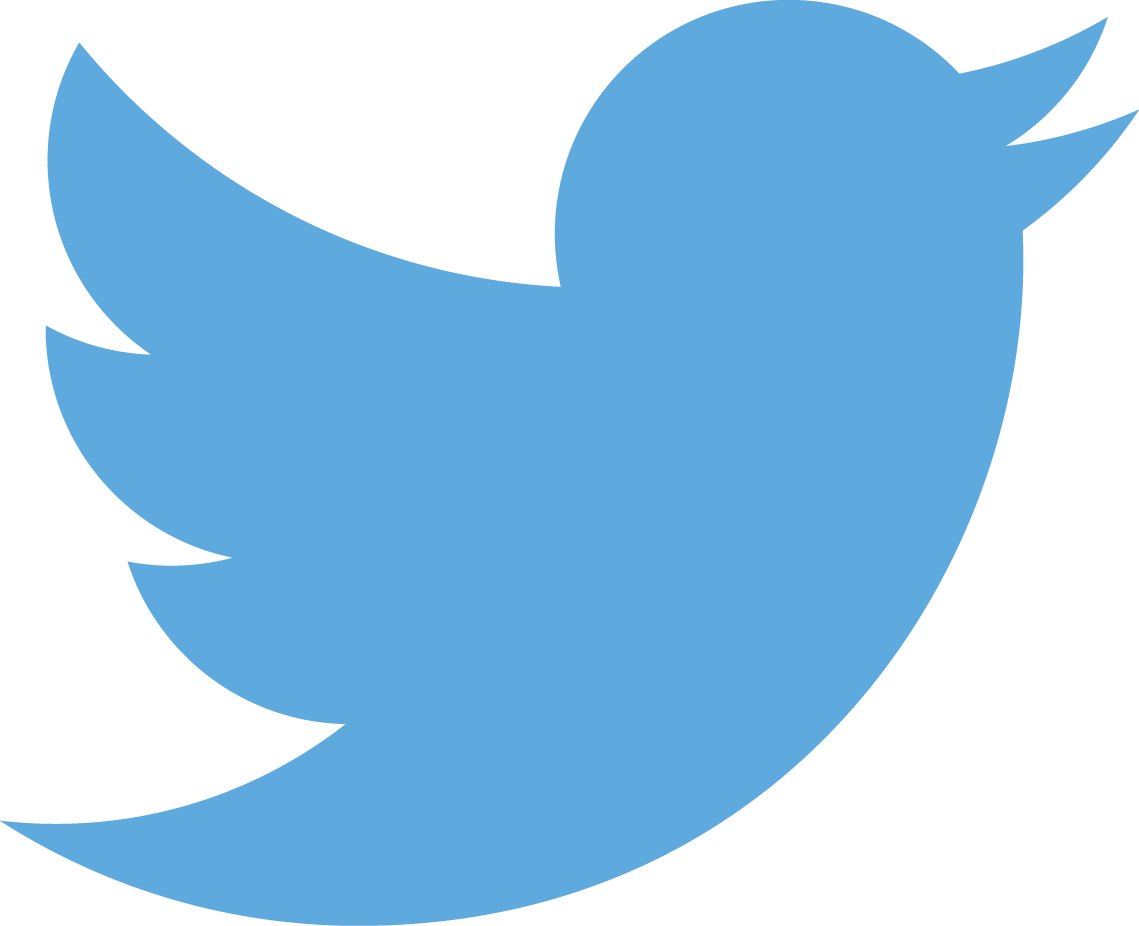ドイツにあるブレーマーハーフェン動物園で飼育されているドッティーとジーというフンボルトペンギンが、ゲイカップルとして10年を迎えました。

10年前に、動物園は二羽ともオスだということを知らずに飼育していました。しかし、2005年にDNA鑑定をしたところ、二羽がオスでありそのために子供ができないことが判明しました。
同動物園において、ペンギンの同性カップルは一組だけではありません。十組のカップル中三組が同性カップルだそうです。動物園は、フンボルトペンギンの絶滅を危惧してメスのペンギンを新たに増やして飼育してみるなど試みた。しかし、結果は試みに反して同性カップルが以前にも増して恋愛関係を持ち始めたそうです。
ドッティーとジーは「家族を作りたい」という意思表示である巣作りを毎年行っているそうです。2009年に、この二羽には母親に捨てられてしまった卵を与えられたそうです。二羽は役割を分担して、卵をかえし、食べ物を与えました。
科学者によると、地球に存在する450種以上の動物に同性愛行動が見られているそうです。
「ゲイ&バイセクシュアル」の動物はたくさん存在しています。子孫繁栄の目的があるから同性愛はありえないという考えは異なっているようです。
例えば、バンドウイルカの場合だと多くの場合がゲイもしくはバイセクシュアルなのです。バンドウイルカは動物の中で最も賢いとされていて、コミュニケーション能力に長けているそうです。
また、オスのブラックスワンのおよそ25%は同性のパートナーと一緒になっています。そのカップルはメスを含めた三羽で性行為に及んで子供を作り、子供を作った後はメスを追い出してオス同士のカップル二羽で育てていくそうです。
このように同性愛・両性愛は人間だけでなく他の動物にも見られるようです。
人間を含め様々な愛の形があり、子供の育て方があることが分かりますね。